読書にはさまざまなスタイルがあります。
その中でも、「多読(たどく)」は、できるだけ多くの本を短期間で読む読書法のことを指します。
多読は、幅広い知識を得たり、新しいアイデアに触れたりするのに適した方法です。
ビジネス書や自己啓発書、時事問題の本などを多読することで、最新の情報を素早く取り入れることができます。
また、小説やエッセイを多読することで、多くの物語に触れ、さまざまな価値観を知ることもできます。
しかし、多読にはデメリットもあります。
たくさんの本を読むことで理解が浅くなったり、記憶に残りにくくなったりすることがあるため、目的に応じて適切に活用することが大切です。
本記事では、「多読」のメリットとデメリットについて詳しく解説し、多読を効果的に活用するためのヒントを探っていきます。
多読のメリット
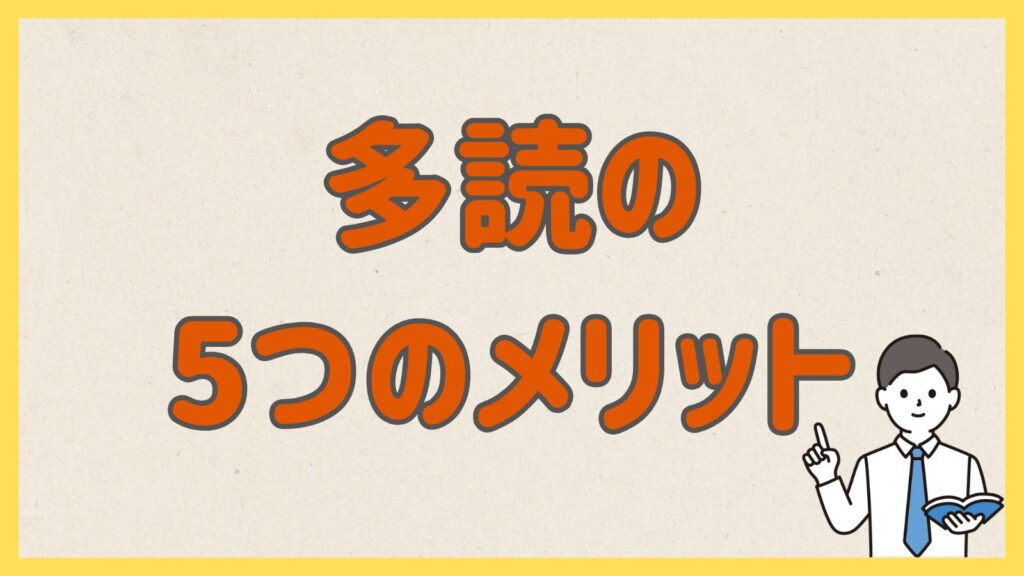
多読は、さまざまな本を短期間で読む読書スタイルです。
そのため、幅広い知識を得るのに適しており、多くのメリットがあります。
ここでは、多読の代表的なメリットを5つ紹介します。
①幅広い知識と視野が身につく
多読の最大の魅力は、さまざまなジャンルの本に触れることで、知識の幅が広がることです。
たとえば、歴史書を読めば過去の出来事について学べますし、ビジネス書を読めば経済の仕組みがわかります。
哲学書を読めば思考力が鍛えられ、科学の本を読めば最新の技術について知ることができます。
このように、多読を続けることで、一つの分野に偏らず、幅広いジャンルの知識を蓄積できるのが大きなメリットです。
具体例
✅ 「歴史 × ビジネス」
→ 過去の経済危機の事例を知ることで、現代の経済動向を理解しやすくなる
✅ 「科学 × 哲学」
→ AI技術の発展について、技術的側面と倫理的側面の両方から考えられるようになる
このように、多読は視野を広げ、新しい発想を生み出すのに役立ちます。
②効率的に基礎知識を習得できる
多読をすると、各分野の基礎知識を素早く得ることができます。
たとえば、ビジネスに関する知識を得たいとき、1冊の専門書をじっくり読むよりも、多くの本を読み比べたほうが、さまざまな視点を得られることがあります。
また、一冊に書かれている情報は限られていますが、多読をすれば複数の本の共通点や違いを比較しながら学べるため、より効果的に知識を吸収できます。
具体例
✅ 「経済学を学びたい」
→ 入門書を何冊か読むことで、経済の基礎がスムーズに理解できる
✅ 「新しい分野に挑戦したい」
→ 初心者向けの本を複数読むことで、短時間で基本を押さえられる
③コミュニケーションの幅が広がる
多読をすると、さまざまな話題についての知識が増えるため、他人との会話や議論がスムーズになるというメリットがあります。
たとえば、異なる分野の本を読んでおけば、相手の専門分野の話にもある程度ついていくことができます。
また、多くの人が読んでいるベストセラーをチェックしておけば、共通の話題を持ちやすくなり、初対面の人とも会話が弾みやすくなるでしょう。
具体例
✅ ビジネスの場面で「最近読んだ本」の話題から会話が広がる
✅ 歴史や文化についての知識があると、外国の人との会話がスムーズになる
✅ 映画やドラマの原作を読んでおけば、エンタメの話題でも盛り上がれる
④速読力・読解力が向上する
多読をすると、文章を読むスピードが自然と速くなり、読解力も向上します。
たくさんの本を読むことで、文の構造や重要なポイントを素早くつかむ力が身につくため、同じ時間内により多くの情報を吸収できるようになります。
また、さまざまな文章スタイルに慣れることで、難解な文章にも抵抗がなくなります。
具体例
✅ 新聞や論文などの長文を速く読めるようになる
✅ 必要な情報を素早く見つけるスキルが身につく
✅ 読解スピードが上がることで、仕事や勉強の効率が向上する
⑤新しい興味・関心が見つかる
多読のもう一つの大きな魅力は、自分が知らなかった分野に興味を持つきっかけになることです。
普段は手に取らないジャンルの本を読んでみることで、思わぬ発見があることもあります。
「このテーマ、意外と面白いな」と思ったら、それが新しい趣味や仕事のヒントになることもあるでしょう。
具体例
✅ たまたま読んだ科学の本がきっかけで、テクノロジーに興味を持つ
✅ 旅行記を読んで、実際にその土地に行ってみたくなる
✅ 自己啓発書を読んで、新しい習慣を取り入れるきっかけになる
📌 まとめ
多読には、以下のようなメリットがあります。
✅ 幅広い知識と視野が身につく
→ 異なる分野の知識を得られる
✅ 効率的に基礎知識を習得できる
→ 短期間で多くの情報を得られる
✅ コミュニケーションの幅が広がる
→ 会話のネタが増える
✅ 速読力・読解力が向上する
→ 重要なポイントを素早く理解できる
✅ 新しい興味・関心が見つかる
→ 未知の分野に興味を持つきっかけになる
このように多読には多くのメリットがあります。
しかし、多読にはデメリットもあります。
次の章では、多読のデメリットについて詳しく解説します。
多読のデメリット
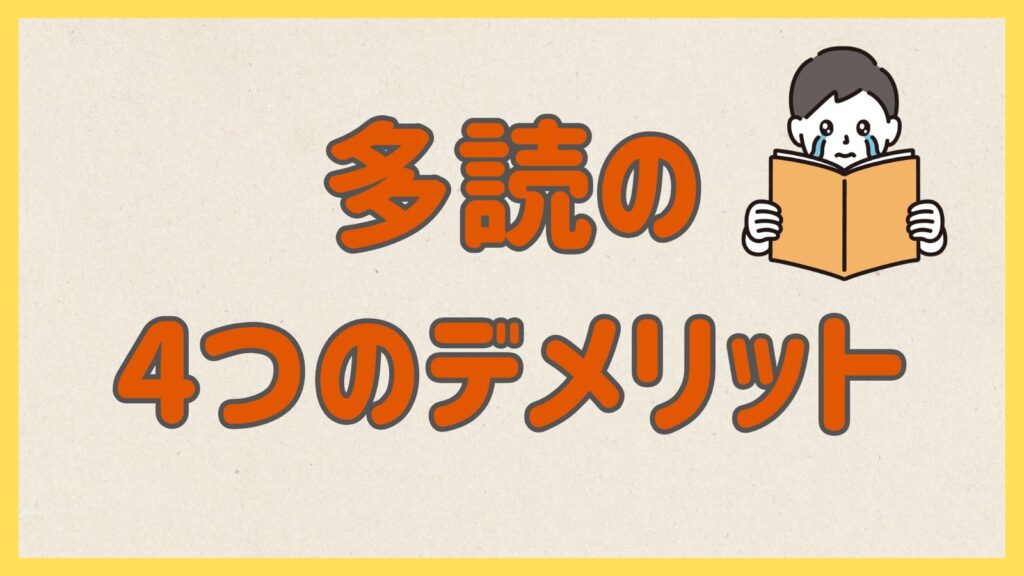
多読には多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。
ここでは、多読の代表的なデメリットについて詳しく解説します。
①理解が浅くなる可能性がある
多読では、1冊にかける時間が短くなるため、深い理解に至らないことがあるのがデメリットです。
特に、専門的な内容や哲学書などのじっくり考えながら読むべき本を多読のスタイルで読んでしまうと、著者の主張や理論を十分に理解できないまま終わってしまう可能性があります。
具体例
✅ 難解な本を飛ばし読みしてしまい、本質を理解できなかった
✅ 深く考えずに次々と本を読んだ結果、知識として定着しなかった
解決策
💡 重要な本は精読する
→ 深く学びたい本はじっくり読む
💡 後から復習できるようにメモを取る
→ 要点を書き留めておくと理解が深まる
②記憶に残りにくい
多読は短期間で多くの情報を得ることができますが、その分、内容を忘れやすいというデメリットもあります。
情報を定着させるには、繰り返し考えたり、何度も復習したりすることが重要です。
しかし、多読では次々と新しい本を読んでいくため、以前読んだ本の内容が記憶に残りにくくなることがあります。
具体例
✅ 1カ月で10冊読んだが、具体的な内容を思い出せる本が少ない
✅ 読んだ直後は「面白かった」と思ったが、時間が経つと忘れてしまった
解決策
💡 読書ノートをつける
→ 読んだ本のポイントを記録しておく
※読書ノートの書き方を知りたい場合はこちらから
💡 アウトプットを意識する
→ 人に話す、SNSで感想を書くと記憶に残りやすい
③感動や共感が薄れる可能性がある
物語やエッセイなどを多読すると、一つひとつの作品をじっくり味わう時間が減るため、感動や共感が薄れてしまうことがあるのもデメリットです。
たとえば、小説をじっくり読めば登場人物に深く共感し、物語の世界観に没入できます。
しかし、多読のスタイルで次々と読み進めてしまうと、一つの作品に対する感動が浅くなり、物語を「消費」してしまう感覚になることがあります。
具体例
✅ 感動的な小説を読んでも、すぐに次の本へ移ってしまい、じっくり味わえなかった
✅ 以前読んだ作品の登場人物の名前やストーリーを忘れてしまった
解決策
💡 特に印象に残った本は、再読する
→ 時間をおいてもう一度読むと、より深い感動が得られる
💡 感想を文章にまとめる
→ 自分の言葉で表現することで、印象に残りやすくなる
④情報量が多すぎて処理しきれないことがある
多読をしていると、次々と新しい情報が入ってくるため、どれが本当に重要なのか分からなくなることがあります。
特に、ビジネス書や自己啓発書を大量に読む場合、「この本にはこう書かれていたけど、別の本では違うことが書かれていた」と混乱することがあります。
情報過多になると、せっかく読んだ内容をうまく活用できないまま終わってしまうこともあります。
具体例
✅ さまざまな本を読んで知識は増えたが、結局どれを実践すればいいのか分からなくなった
✅ 読書を続けるうちに、「もっと読まなければ」という焦りを感じるようになった
解決策
💡 本のジャンルやテーマを絞る
→ 闇雲に読むのではなく、目的を持って選ぶ
💡 定期的に振り返る時間を作る
→ 読書した内容を整理し、実践につなげる
📌 まとめ
多読にはいくつかのようなデメリットがあります。
✅ 理解が浅くなる可能性がある
→ じっくり考えずに読んでしまう)
✅ 記憶に残りにくい
→ 読んだ内容をすぐに忘れてしまう)
✅ 感動や共感が薄れる可能性がある
→ 本を「消費」する感覚になりがち
✅ 情報量が多すぎて処理しきれないことがある
→ どの情報が重要か分からなくなる
しかし、これらのデメリットは、多読の方法を工夫することで克服できます。
次の章では、多読のメリット・デメリットをふまえて、どのように活用するのが最適かをまとめます。
まとめ
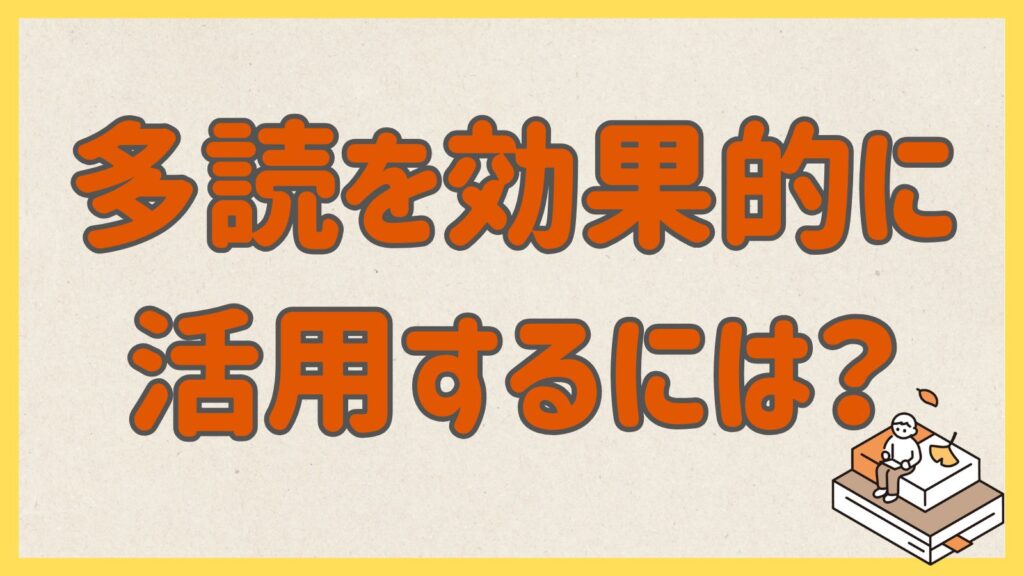
本記事では、たくさんの本を読む「多読」について、そのメリットとデメリットを詳しく解説しました。
多読のメリット
多読には、以下のようなメリットがあります。
⭕ 幅広い知識と視野が身につく
→ さまざまな分野の知識を効率的に得られる
⭕ 基礎知識を短期間で習得できる
→ 多様な視点を比較しながら学べる
⭕ コミュニケーションの幅が広がる
→ 知識が増え、会話の引き出しが増える
⭕ 速読力・読解力が向上する
→ 文章の要点を素早くつかめるようになる
⭕ 新しい興味・関心が見つかる
→ 未知の分野に興味を持つきっかけになる
多読のデメリット
一方で、多読には以下のようなデメリットもあります。
❌ 理解が浅くなる可能性がある
→ じっくり考えずに読んでしまう
❌ 記憶に残りにくい
→ 読んだ内容をすぐに忘れてしまう
❌ 感動や共感が薄れる可能性がある
→ 本を「消費」する感覚になりがち
❌ 情報量が多すぎて処理しきれないことがある
→ どの情報が重要か分からなくなる
多読を効果的に活用するには?
多読のメリットを最大限に活かしながら、デメリットを克服するためには、他の読書法とバランスよく組み合わせることが重要です。
①精読と多読を使い分ける
✅ じっくり理解したい本
→ 精読向き(深く考えながら読む)
✅ 幅広い知識を得たい本
→ 多読(効率的に読み進める)
②読書ノートを活用する
✅ 読んだ本の要点を簡単にメモすることで、記憶に残りやすくなる
✅ 読書後に感想をSNSやブログに書くのも効果的
※読書ノートの書き方を知りたい場合はこちらから
③「読むだけ」で終わらせない
✅ 読んだ内容を実生活や仕事に活かせるよう、アウトプットを意識する
✅ 他人と本の内容について話すことで、理解が深まる
📚 おわりに
多読は、情報収集の効率を高め、知識の幅を広げるのに適した読書法です。
一方で「理解が浅くなる」「記憶に残りにくい」などの課題もあります。
大切なのは、読書の目的に応じて精読と多読を使い分けることです。
次回の記事では、「精読」と「多読」の違いを比較し、それぞれの活用法についてさらに詳しく解説します。
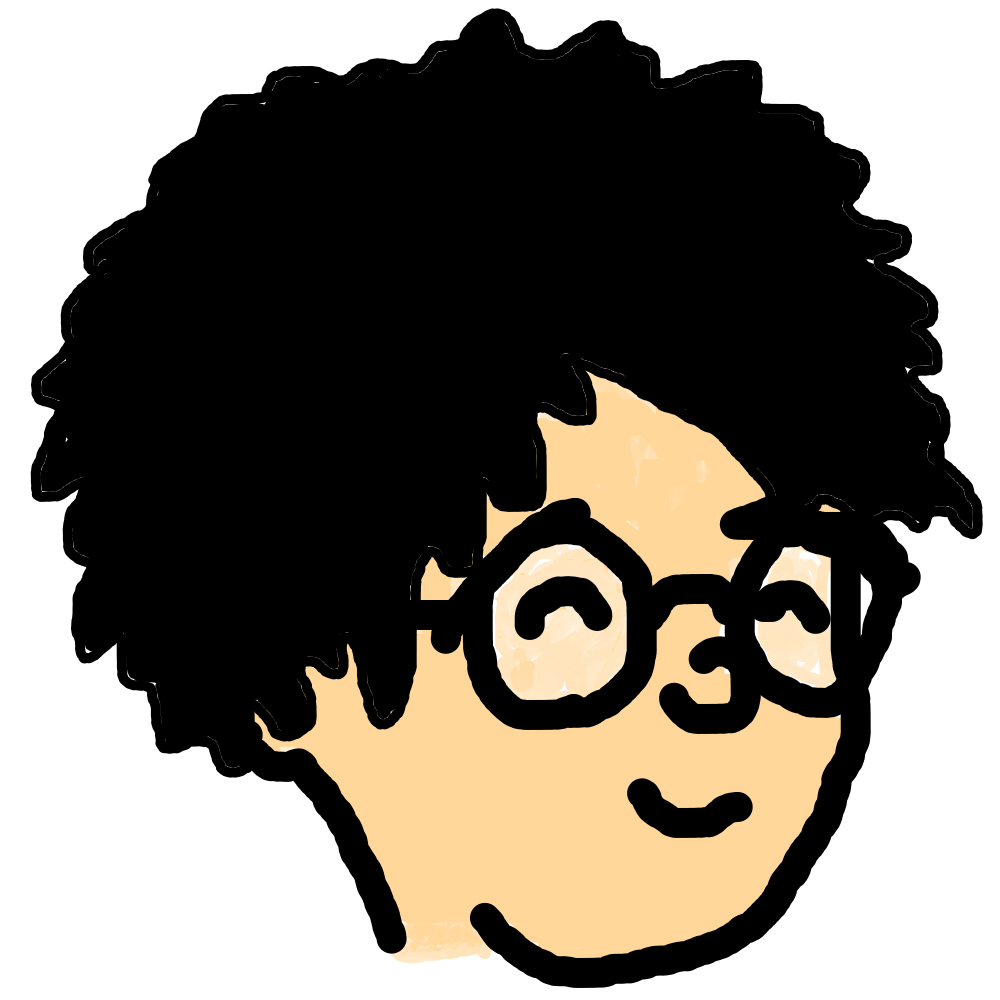
自分に合った読書スタイルを見つけ、より充実した読書ライフを楽しんでいきましょう!

あなたは多読についてどう思いますか?
ぜひコメントで教えてね😊

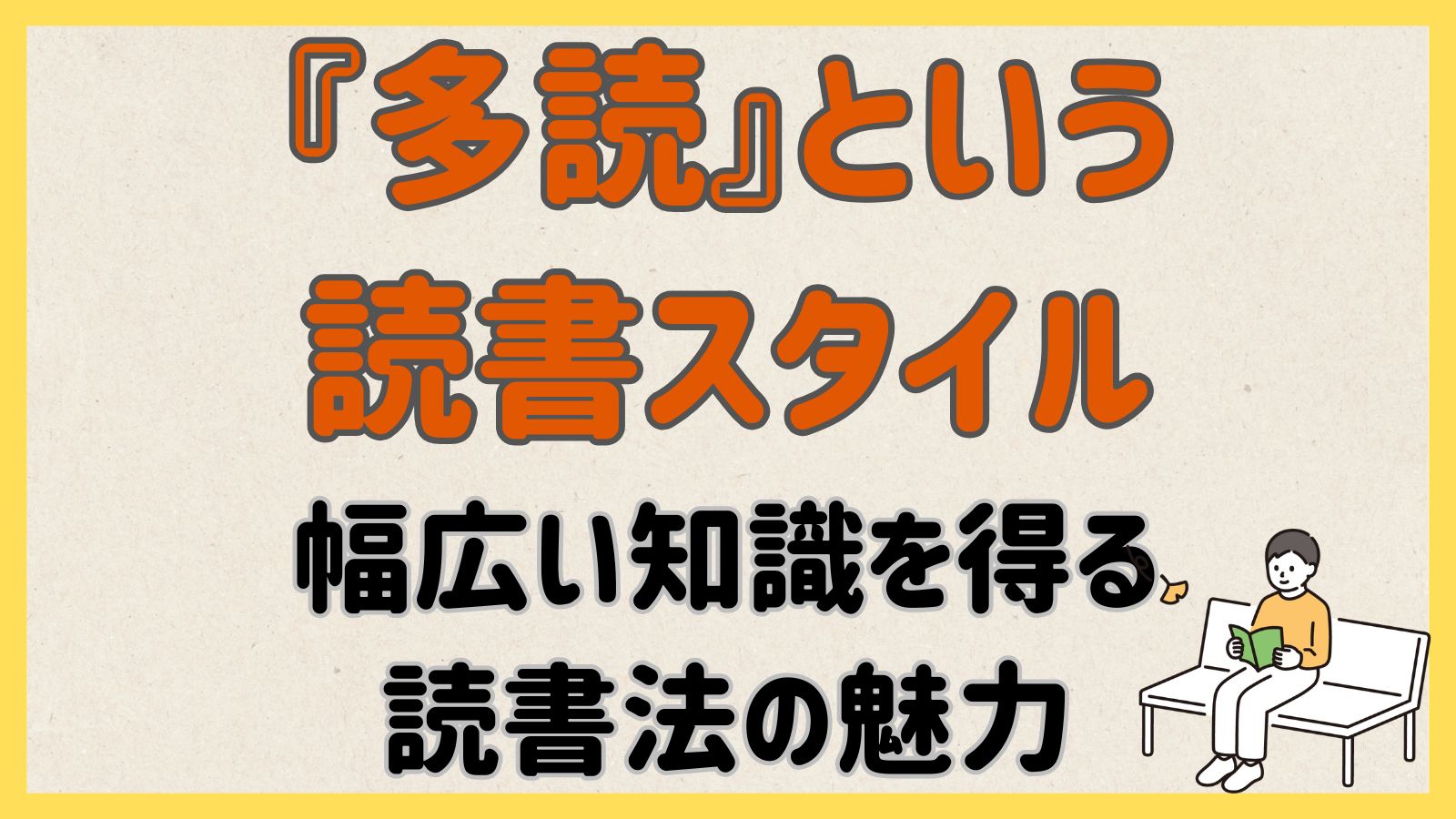
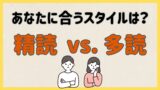
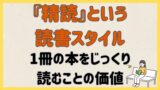
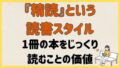
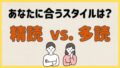
コメント