何かに挑戦するとき、つい「自分にできるだろうか」と考えてしまうことはありませんか?
でも、できるかどうかよりも「やってみること」こそが大切なのかもしれません。
『線は、僕を描く』は、水墨画という世界を通じて、自分と向き合い、成長していく青年の物語。
そこには、人生を前に進めるためのヒントがたくさん詰まっています。
今回は、本作の魅力や、そこから得られる人生観について深掘りしていきます。
オススメ度について
このブログでは、映画や書籍のオススメ度を5段階で評価しています。
各評価の基準については、こちらでご確認いただけます。
作品概要

| 作品名 | 線は、僕を描く |
| 著 者 | 砥上裕將 |
| ジャンル | 青春小説 |
| 発行日 | 2019年6月27日 |
| ページ数 | 337ページ |
「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」
両親を亡くし、深い悲しみの中にいた大学生・青山霜介。
アルバイト先の展示会場で水墨画の巨匠・篠田湖山と出会い、ひょんなことから弟子入りすることになります。
反発する湖山の孫娘・千瑛との確執、初めて触れる水墨画の世界。
そして、一年後に開かれる「湖山賞」での勝負。
霜介は水墨画を通じて、自分自身と向き合いながら、次第に前へ進んでいくのです。
作品から学べる教訓・人生観(感想)
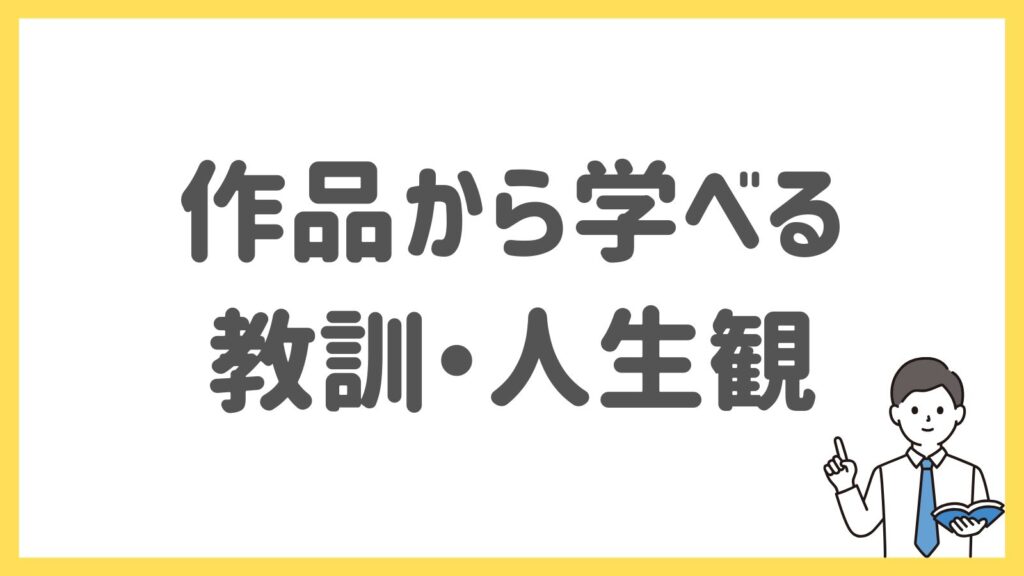
①記憶に囚われた青年の成長
混乱と苦しみが頂点に達したとき、気づくと僕は、実家のリビングにいながら、同時に真っ白な部屋の中にいた。
砥上裕將(著)線は、僕を描く より引用
そこは僕の心の中にだけ存在する場所だったけど、そこでなら僕は少しだけ元気でいられた。
僕は壁を少し叩いてみた。質感はガラスそのものだった。(中略)
僕が本当に安らぐことのできる場所は、この場所で見る記憶だけになった。
ただ記憶を眺め続けた。
ガラスの内側に映る景色だけを、ずっと眺めて過ごしていた。
本作の主人公・霜介は、両親を亡くした悲しみから抜け出せず、現実を生きることに意味を見出せずにいました。
彼の心はまるで「ガラスの中に閉じ込められている」ような状態。
この比喩表現が、霜介の心理を鮮明に描き出しています。
現実と記憶の狭間にいる彼の苦しみや孤独は、読者にも強く共感できるものでしょう。
しかし、彼は水墨画と出会い、少しずつ変わり始めます。
②「やってみる」ことの大切さ
できることが目的じゃないよ。
砥上裕將(著)線は、僕を描く より引用
やってみることが目的なんだ。
「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」
これは篠田湖山が霜介にかけた言葉です。
新しいことに挑戦するとき、多くの人は「自分にできるだろうか?」と不安を抱えます。
しかし、大切なのは「やってみる」こと。
霜介も最初は「水墨なんて自分にできるはずがない」と思っていました。
でも、湖山の言葉を受け入れ、筆を握ることで、少しずつ世界が変わっていきます。
これは、何かに挑戦しようとするすべての人に響くメッセージではないでしょうか。
水墨画の持つ「自由さ」と「世界の美しさ」
いつも何気なく見ているものが実はとても美しいもので、僕らの意識がただ単にそれを捉えられないだけじゃないかって思って……。
砥上裕將(著)線は、僕を描く より引用
絵を描き始めてから僕はようやく何かを見ることができるようになったんだって思いました。
水墨画には、描かれていない余白にすら意味があります。
それはまるで、人生そのもの。
すべてを埋め尽くさず、余白を残すことで、そこに広がる無限の可能性を感じられるのです。
霜介が水墨画と向き合い、心を開いていく様子は、「世界の美しさに気づくこと」「自由な表現がもたらす解放感」 を象徴しているように思えます。
なぜこの作品がオススメなのか
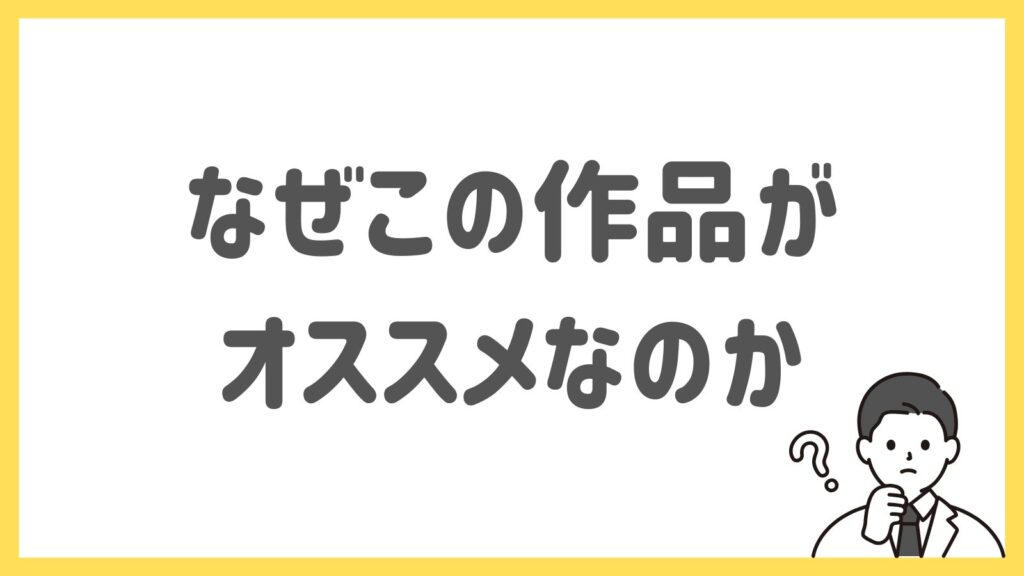
世界を見る目が変わるような体験
『線は、僕を描く』は、
- 自分の心と向き合いたい
- 人生の意味をもう一度考えたい
- 何か新しいことに挑戦したい
そんな人にぴったりの作品です。
表現の美しさが際立ち、世界を見る目が変わるような体験ができます。
総評・まとめ
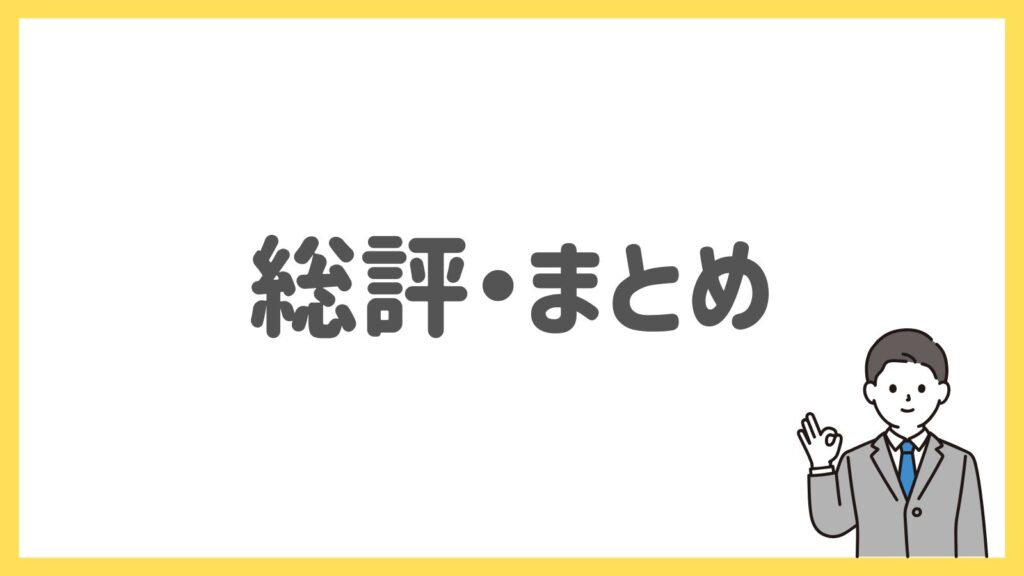
君が生きる意味を見いだして、この世界にある本当にすばらしいものに気づいてくれれば、それだけでいい。
砥上裕將(著)線は、僕を描く より引用
本作は、水墨画というテーマを通して、人生の本質に迫る物語です。
霜介の成長や、湖山の言葉からは、「挑戦することの大切さ」や「世界の美しさを感じること」が学べます。
読後には、自分の人生にも何か新しい風が吹き込むかもしれません。
『僕は、線を描く』のオススメ度は⭐4です!
完成度が高く、このジャンルが好きならより楽しめる作品。

表現の美しさが際立ち、世界を見る目が変わる体験ができるような作品です。

深みがあるストーリーだけどシンプルだからエンタメ性を求める人には物足りなく感じるかもね。
こんな人にオススメ

- 前向きに生きる力を見つけたい人
- 自己成長や人生観に関心がある人
- 静かに心を揺さぶる作品が好きな人
『線は、僕を描く』は、人生の中で何かを見失いかけたとき、 静かに寄り添い、前へ進む力をくれる一冊です。

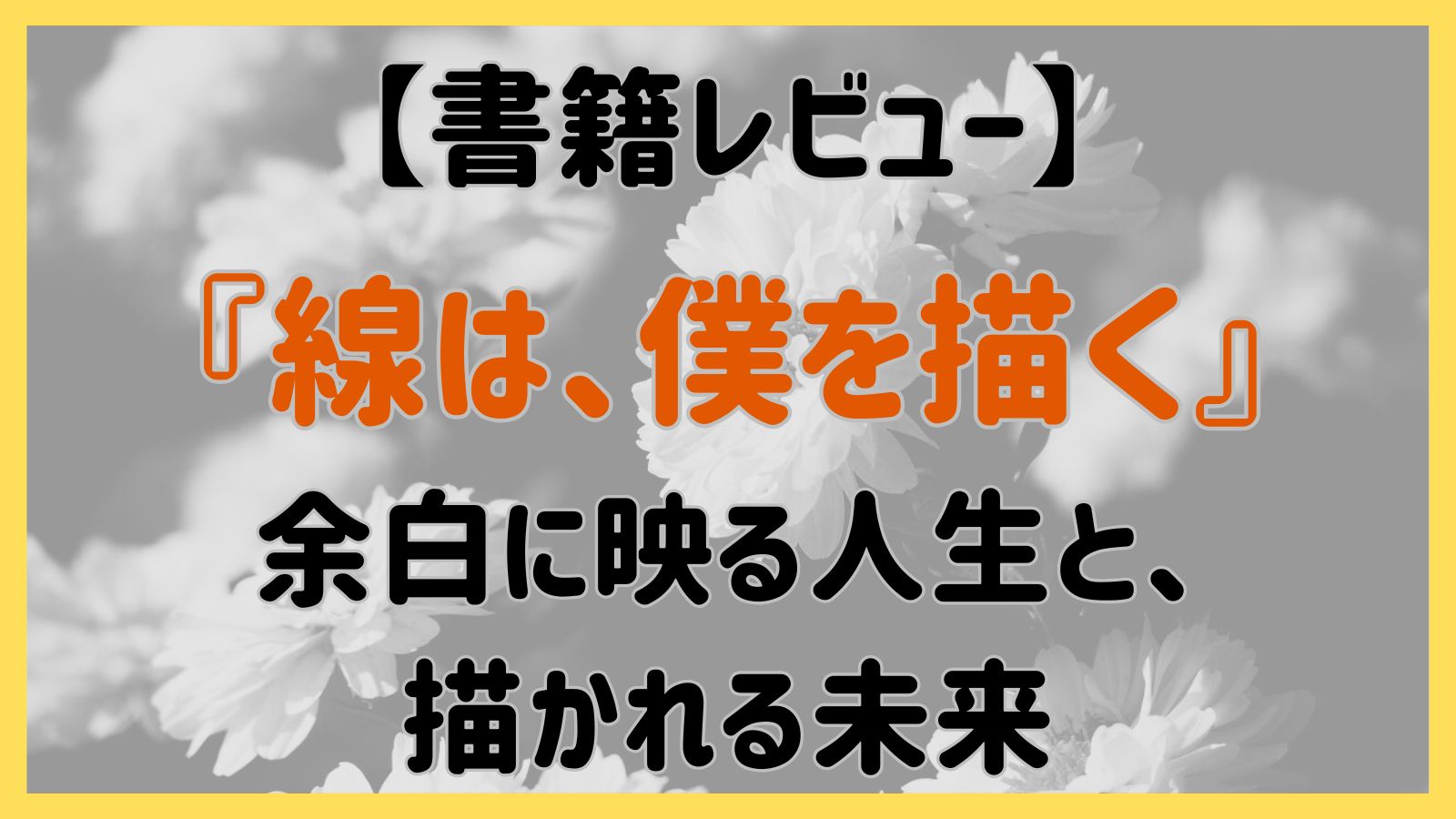

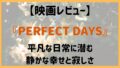
コメント