あなたは「言葉」について深く考えたことがありますか?
普段何気なく使っている日本語。
しかし、それが誰にとっても当たり前の共通言語とは限らない――。
『デフ・ヴォイス』は、ろう者と聴者の間で揺れる主人公・荒井尚人の視点を通して、「言語」と「アイデンティティ」の境界を浮かび上がらせる作品です。
ミステリー要素を含みつつ、ろう者の文化や手話という「もうひとつの言語」に光を当てた本作は、単なるエンタメ小説ではなく、読者に深い問いを投げかけます。
つまり、ろう者にとっての言葉とはあくまで「日本手話」のことであり、「日本語」は「第二言語」に過ぎない。
丸山正樹(著)デフ・ヴォイス より引用
作品概要

| 作品名 | デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士 |
| 著 者 | 丸山正樹 |
| ジャンル | ミステリー |
| 発行日 | 2011年7月25日 |
| ページ数 | 271ページ |
埼玉県警の元事務職員・荒井尚人は、再就職先が見つからず、深夜の警備員として働く日々を送っていた。
幼い頃からろうの両親の通訳をしてきた彼は、しぶしぶ手話通訳士の資格を取得し、仕事を始めることに。
そんなある日、窃盗未遂で起訴されたろう者の法廷通訳を依頼される。
ろう者と聴者、それぞれの世界に挟まれた尚人は、自身のアイデンティティに揺れながら、事件の真相に迫っていく……。
「手話には『日本手話』と『日本語対応手話』の二つがある」
丸山正樹(著)デフ・ヴォイス より引用
「先天性の失聴者の多くは誇りを持って自らを『ろう者』と称する」
作品から学べる教訓・人生観(感想)
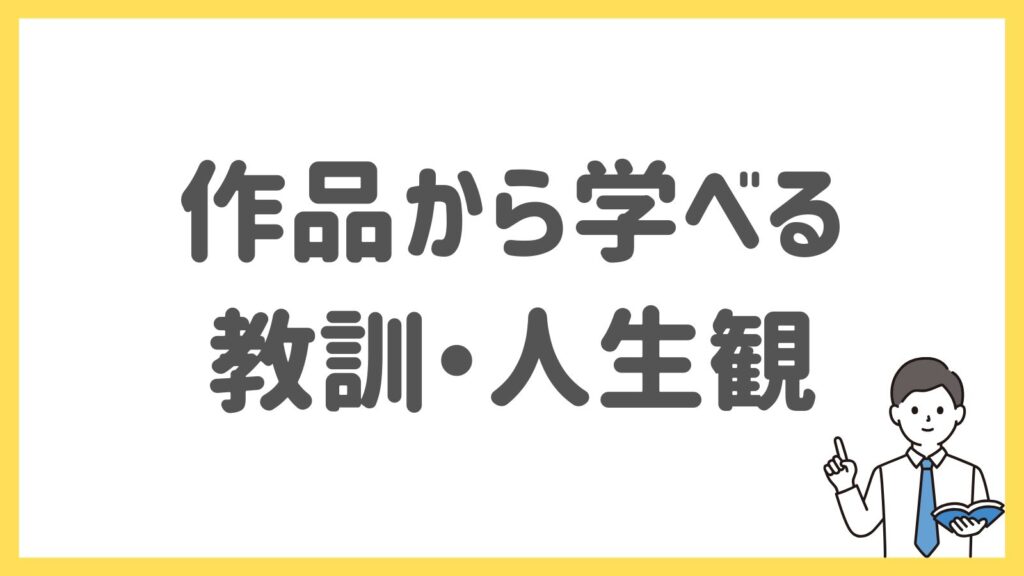
①ろう者と聴者、そしてコーダの視点
コーダ、つまり「両親ともにろう者である聴こえる子」の場合、音声日本語より前に、日本手話を自然に習得します。
丸山正樹(著)デフ・ヴォイス より引用
(中略)
たとえ音声日本語を話す「聴者」であっても、本質的に彼らは「ろう者」であると言えます。
『デフ・ヴォイス』では、言葉の持つ意味や、それがアイデンティティに与える影響が丁寧に描かれています。
「聴覚障害者」という言葉は、単に「障害」にフォーカスしているため、ろう者の文化や生き方を表現しきれません。
その一方で、「コーダ(Child of Deaf Adults)」という言葉を知った尚人は、自分が特別ではなく、同じ境遇の人々がいることを実感します。
名称が持つ力――
それが他者とのつながりを生み、自分自身を肯定するきっかけにもなることを、この作品は教えてくれます。
② 荒井尚人の孤独
ああ、あなたは聴こえるのね。
丸山正樹(著)デフ・ヴォイス より引用
そこには、一握りの羨望とともに、落胆と拒絶の色が宿る。
(中略)
荒井の周りには、いつしか誰もなくなっていた。
主人公の尚人は、ろう者と聴者、どちらの世界にも完全には属せない「中間者」です。
人は本能的に「自分の居場所」を求めます。
しかし、尚人のようにどちらにも属せない存在は、強い孤独を抱えがちです。
ただし、それは「二つの世界を理解できる」という強みでもあります。
この作品を通して、「どちらかに属さなければならない」という思い込みから解放されるヒントを得られるかもしれません。
③味方か敵か――分断を超えた理解
おじさんは、私たちの味方?それとも敵?
丸山正樹(著)デフ・ヴォイス より引用
『デフ・ヴォイス』では、登場人物たちが「敵か味方か」という視点で人を判断する場面が目立ちます。
しかし、作中で尚人が直面する問題は、「分断の先にある理解」についても考えさせます。
閉じた世界にいると、「自分たちを理解してくれる人」と「理解しない人」という二極化が進みがちですが、それでは対立が深まるばかり。
本作は、名称や立場による線引きを超え、「真の対話とは何か」を問いかける作品でもあります。
なぜこの作品がオススメなのか
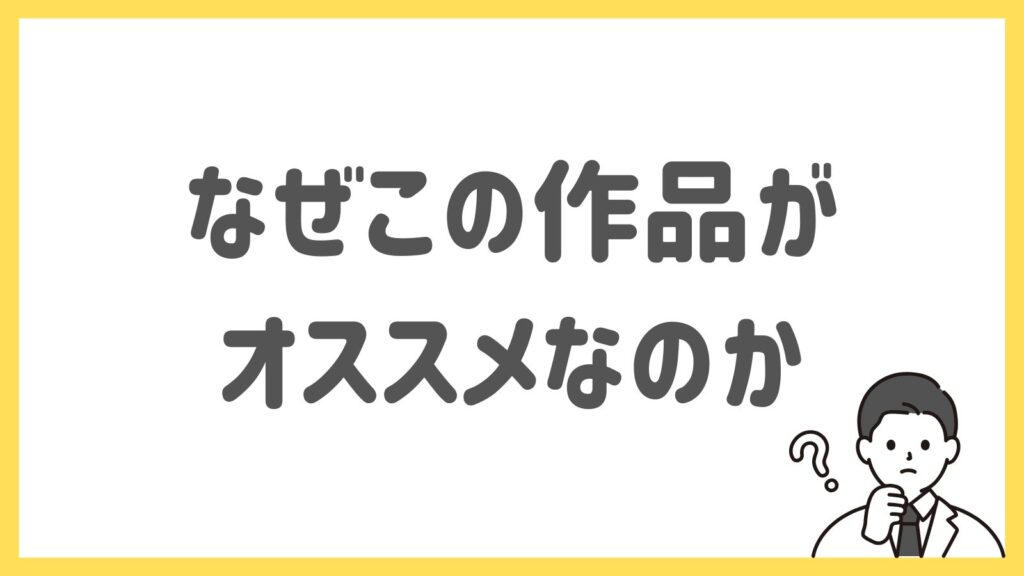
『デフ・ヴォイス』は、ろう者の文化や手話が物語の中心に据えられた、他に類を見ない作品です。
- リアルな社会問題を扱っている
- 言語やアイデンティティについて深く考えさせられる
- ミステリー要素がありつつも、人間ドラマが魅力的
一方で、派手なトリックやどんでん返しを期待すると、やや物足りなさを感じるかもしれません。
人間ドラマに重きを置いた作品なので、ミステリーよりも人生観に興味がある人向けです。
総評・まとめ
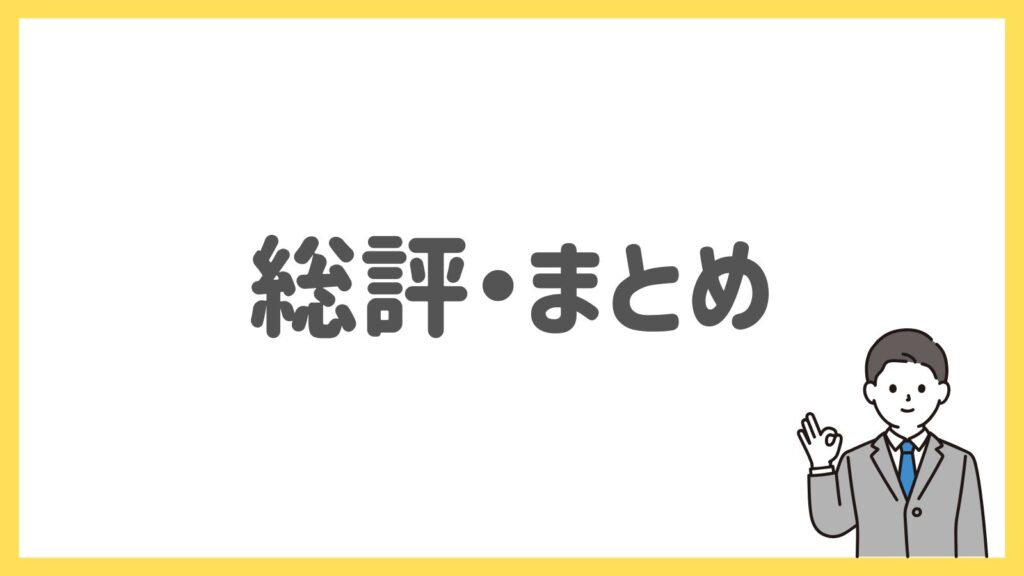
『デフ・ヴォイス』は、手話通訳士という珍しい職業を軸に、ろう者と聴者の間にある文化的な違いを浮き彫りにする作品です。
荒井尚人という「中間者」の視点を通じて、私たちが普段意識しない「言葉の壁」や「所属するコミュニティへの帰属意識」について深く考えさせられます。
派手な展開やエンタメ性は低めですが、じっくりと味わいながら読む価値のある一冊です。
『デフ・ヴォイス』のオススメ度は⭐4です!
完成度が高く、このジャンルが好きならより楽しめる作品。

ろう者の文化や手話のリアルな描写が素晴らしく、アイデンティティや孤独について考えさせられる人間ドラマとしての完成度が非常に高い作品です。

ただしミステリー要素は薄く、エンタメ性は控えめなので、そこは要注意だね。
こんな人にオススメ

- 言語やコミュニケーションに関心がある人
- 哲学的なテーマや人生観を考えさせられる作品が好きな人
- じっくり読める作品を求めている人
『デフ・ヴォイス』を読めば、「言葉とは何か?」を改めて考えさせられるはずです。
普段、何気なく使っている言語が、実は「当たり前」ではないと気づいたとき、あなたの世界は少し広がるかもしれません。

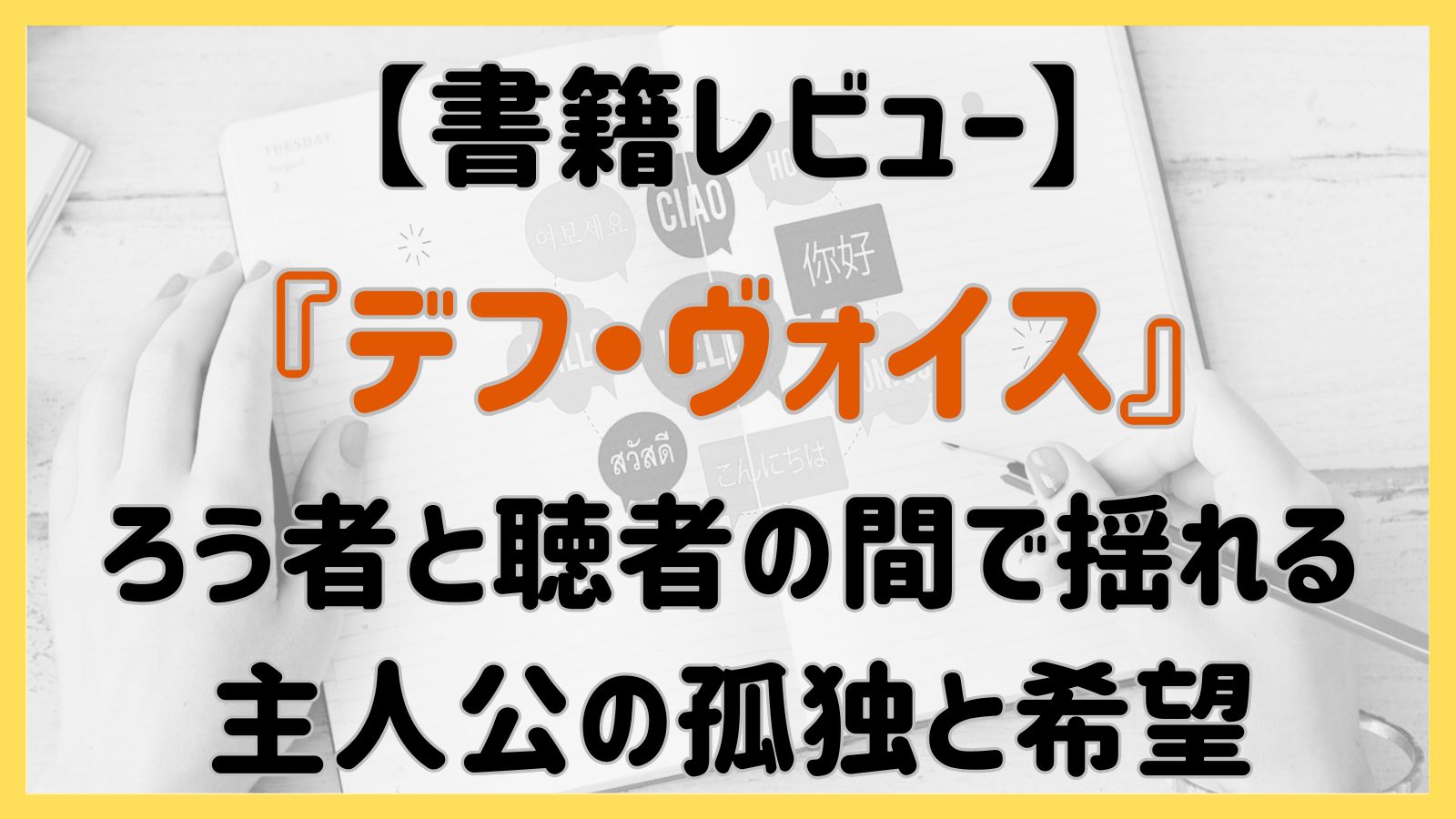

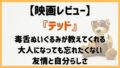
コメント