☆面白い本を探している人に向けた記事
夢枕獏(著)「餓狼伝Ⅳ、餓狼伝Ⅴ、餓狼伝Ⅵ、餓狼伝Ⅶ」を読みました。
本書を読むかどうか迷っている人、次に読む小説を探している人は、この記事を参考にしていただけたらと思います。

作品概要
餓狼伝は夢枕獏氏により1985年より書き下ろされた格闘技小説です。
餓狼伝Ⅳが双葉社より1992年4月10日、餓狼伝Ⅴが1995年3月10日、餓狼伝Ⅵが1997年4月11日、餓狼伝Ⅶが1998年1月12日に発売されています。
餓狼伝は、漫画化、映画化に加えゲーム化もされているメディアミックス作品でもあります。
板垣恵介氏の作画による漫画版も有名で、私も少し読んだことがありますが、登場人物の設定や物語は若干違っていて、あくまで同小説を原作とした漫画といった感じです。
「”あいつとこいつとはどちらが強いのか”執筆同時には存在しなかったリアルな格闘技小説が餓狼伝です。」
著者である夢枕獏氏は、餓狼伝Ⅰのあとがきにそう書いています。
夢枕獏氏には本格的な格闘技経験はなく、格闘技の素人がどこまで人と人との戦いを書けるか、に挑戦したそうです。
餓狼伝Ⅳは、餓狼伝Ⅱ以降がそうであるように主人公丹波文七とその周りの、丹波に影響された、丹波をきっかけに動き出した出来事を描いています。
餓狼伝Ⅴ、餓狼伝Ⅵ、餓狼伝Ⅶでも同じように丹波をきっかけにした出来事や丹波に関係する人物の物語が描かれていますが、巻を重ねるにつれ、丹波以外の人物や業界の出来事や物語の描写は増えていき、群像劇のような様相も強まっていきます。
感想
丹波文七の魅力
餓狼伝の主人公は丹波文七である。
餓狼伝の物語は、全て、丹波をきっかけに丹波を中心として動いている。
丹波が意図的にそうしているのではない。丹波と丹波の戦いに周りは影響されている。
丹波が丹波の周囲や関係している人、格闘技の業界を変えたのは確実だ。
それは丹波の願望ではあるのかもしれないが、意思ではない。
丹波文七という人物とその戦いにはそれだけの、人の感情に作用するような行動をさせるような力と魅力があるのだろう。
読者と同じように、物語の登場人物たちも丹波文七を魅力的に感じ、そして影響されているのだ。
さらに深まる各登場人物の物語
丹波に影響されて行動する登場人物たち。
餓狼伝では都度その登場人物たちにスポットが当たる。
そして視点が変わるたびにその登場人物の魅力が引き出されていく。
餓狼伝Ⅲまでの主要人物、丹波と戦ったプロレスラーの梶原年男、竹宮流の藤巻十三はもちろんだが、物語で大きな存在感を見せているが丹波とは正式に戦っていない猛者たちも例外ではない。
グレート辰巳、松尾象山、姫川勉なども、物語が進んでいくにつれて、どんどんその魅力が引き出されていく。
人間一人ひとりにはさまざまな物語がある。
知らない誰かにも、知っているあの人も、同様である。
現実の人間がそうであるように、餓狼伝の登場人物にもさまざまな物語があり、それが描かれる。
著者夢枕獏氏の描く登場人物の物語は、とても面白く魅力的だ。
登場人物を知れば知るほど、餓狼伝の深みにはまっていく。
あの登場人物の過去と現在、そして未来。
あいつとあいつが交わったらどうなるのか…際限がない。想像するだけでワクワクする。
最強とは
餓狼伝にはさまざまな格闘家が登場する。プロレス、空手、柔道、ボクシング、ムエタイ、古武術…世界には数多くの格闘技があって、どの格闘技が最強の格闘技なのか、というのも餓狼伝のテーマの一つである。
もちろんそれを駆使する人物が誰かということも重要だが、それを抜きにして考えるのもまた面白いと思う。
餓狼伝において、強さは、一つだけの要素や要因だけでは決まらない。
その人物が持つ技術、肉体の強さ、信念や精神力、勝ちたいと思う執念など、さまざまな要素と要因の複合である
またその時の状態や運もかかわってくる。餓狼伝の戦いでは、誰が勝つか、本当にわからない。
主人公の丹波ですら、勝つことも負けることも(もしくは勝負がつかない)有り得る。
そして勝っても負けてもその後どうなるかがまったく見当がつかない。
想像がつかない勝負や展開は本当に面白いし、読んでいて楽しい。
試合と死合
戦いには大きく分けて2種類がある。
レフェリーがいてルールがあるものと、戦いの当事者同士だけのなんでもありのもの。
餓狼伝では前者を試合、後者を死合と呼んでいる描写がある。
物語が進んでいくにつれて徐々に試合の比率が増えていく。それは悪いことではない。
試合であれば、戦う理由も勝ち負けも分かりやすいし、なによりたくさんの者同士、戦う機会が増えるため、読者の楽しみも増す。
試合であっても戦いと当事者の心情の描写は凄まじく、熱い。しかし死合に比べると緊張感が幾分かは小さい。
餓狼伝の死合は壮絶だ。その結果により再起不能になったり、場合によっては死すらも有り得る。
試合よりも緊張感がすごくて、読んでいて手に汗を握る。気持ちもより一層昂る。
試合の比率を増やすことで、相対的に戦いの機会も増える。
それにより登場人物が持つ強さを表現する機会も増える。試合が増えているのにはそういった理由もあるのかもしれない。
しかも試合が増えると死合の描写がより映える、といった効果もあると思う。
あとがきに書いてあったことだが、著者夢枕獏氏も迷っているらしい。どちらを勝たせるべきなのか、どちらが強いのか…。
広がり続ける餓狼伝の物語
餓狼伝Ⅶの前半で、餓狼伝Ⅱから続いた物語は一応の区切りを迎えている。
しかし物語の大きなテーマである強さについてはまだまだ結論には程遠い。
餓狼伝Ⅱからの明言されていた出来事のひとつが、とりあえず終わった程度でしか進んでいない。
しかも餓狼伝Ⅶはそのほとんどを次巻以降の布石に使っているのである。
餓狼伝Ⅶでは、それまでの過去と現在の物語を踏み台にして、さらに世界が広がっていく。
丹波をきっかけにした動きは、巻き込む人間の種類と規模をさらに大きくしていく。
著者夢枕獏氏は餓狼伝Ⅶのあとがきで「まだ、あと二巻を書かなければこの物語は決着がつきそうにない」と書いてある。嘘だ。
絶対にあと二巻で終わるはずがない。それどころか区切りもつかないと思う。もう騙されない。
すごく楽しみだ。
あとがき的なものとオススメ度
餓狼伝は餓狼伝Ⅰで一区切り、餓狼伝Ⅱから餓狼伝Ⅶで一区切りといった感じになっていますが、次巻以降も新たな展開でまだまだ物語は続いていくようです。
餓狼伝Ⅶのあとがきで著者夢枕獏氏が「あと二巻を書かなければこの物語は決着がつきそうにない」と言っていると書きましたが、併せて次のようなことも書かれています。
もともと、何ごとかに決着がつくというようなことが、そうそうあるはずがない。
生き方そのものに、最終回もゴールもないのだ。
終るとしたら、仮の終りしかない。
およそ、あらゆる物語の最終回は、ある日の作者の死をもって、
いきなり、読者の前に投げ出されるべきではないか。~餓狼伝Ⅶあとがきより~
これはもう覚悟を決めるしかなさそうですね!(笑)
もちろんこれは、終わらせる気がないわけでも、読者に覚悟を決めさせるために書いたのでもないと思います。
私(こうよう)はこれを見て、逆に気が楽になりました。完璧に共感してしまいましたからね。
終わりがあるからこその美しさも理解していますし、物語の完結を見たことによる満足感や達成感は、すごく好きです。
しかし、そんなもんなんですよね。こうでないといけないというのは自分の勝手な思い込みとわがままで、終りの形なんでたくさんあって…。
価値観をひっくり返されたというより、新たに価値観が広がったように思えて、気持ちがよくて、うれしくなりました。
「餓狼伝Ⅳ~Ⅶ」のオススメ度は★4.0です!(満点が★5.0です)
熱い描写が魅力の作品です!読めば読むほど物語に引き込まれます。
巻数を重ねてきて、読み始めるのにちょっと躊躇するかもしれませんが、読んで損はないどころか絶対に面白いと思いますよ。
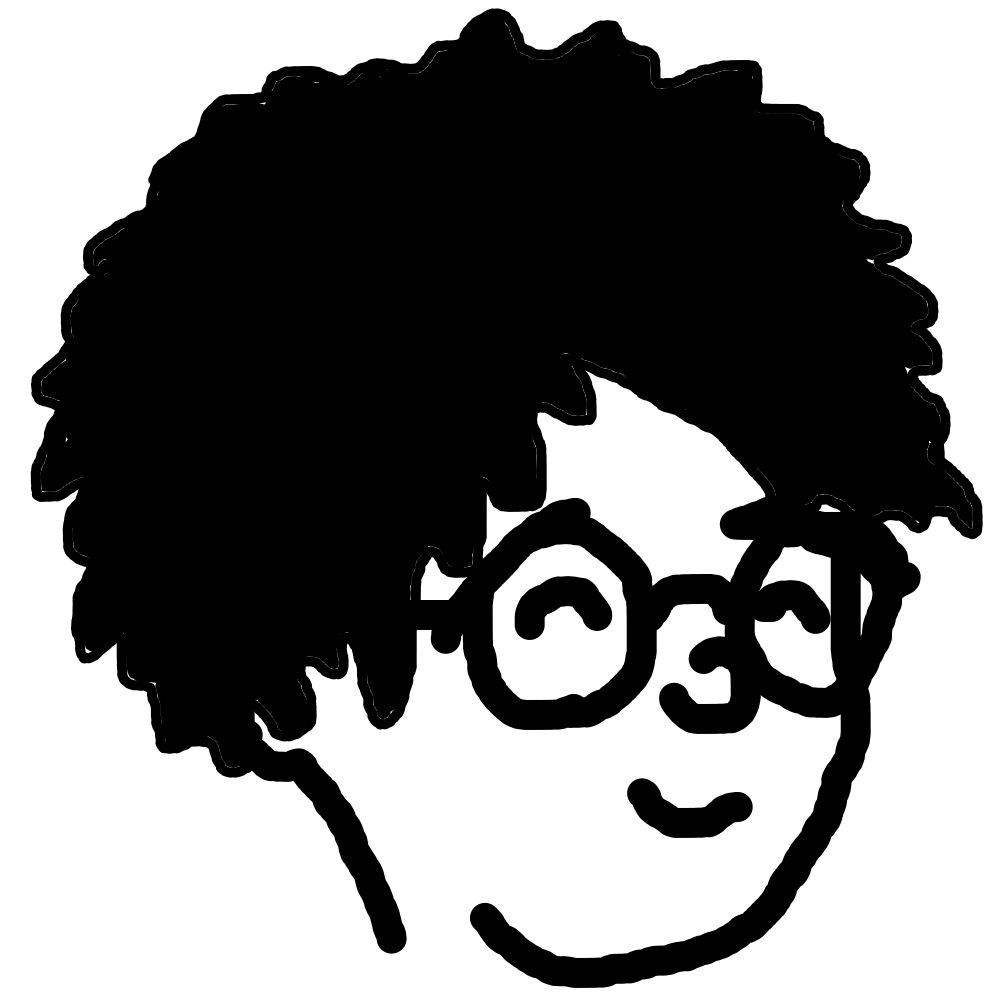
終りが見えなくても不安にならないどころかワクワクする稀有な作品ですね!

なんでも楽しむ気持ちは大事!
こんな人にオススメ
・格闘技に興味がある
・面白くて熱い小説が読みたい
・濃密な小説が読みたい
・完結していなくても構わない



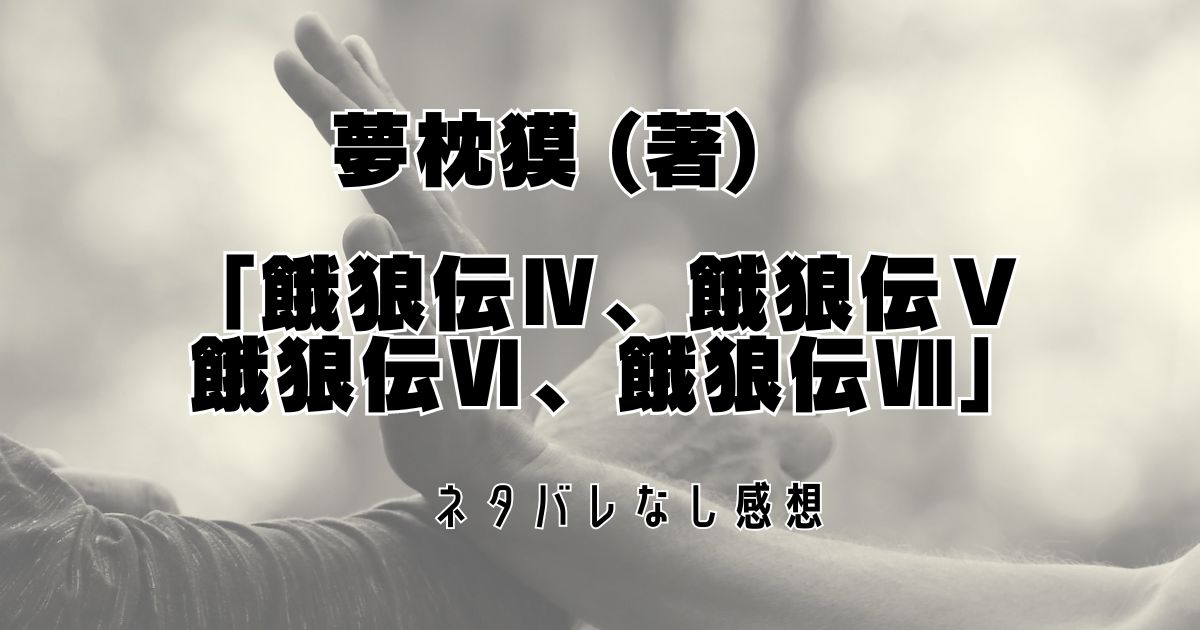

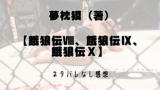

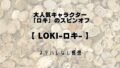
コメント